 当病院について
当病院について


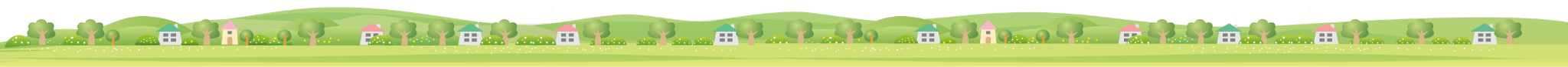



理念
私達は患者様が安心し信頼できる最善の医療を提供し、 患者様の健康の回復と自立の支援に努めます。
基本方針
私達は、
1. 患者様一人ひとりを大切にし、暖かな思いやりのある雰囲気の中で心と心のふれあいを通じて家族と共に真の医療を目指します。
2. 患者様が安心して医療を受けられる様に適正で効果的な治療をします。
3. 強い倫理観と使命感をもってチーム医療を行い患者様の健康の回復と社会復帰に努めます。
4. 地域の皆様の健やかな暮らしと健康のために貢献します。
5. ノーマライゼーションの理念に基づき、すべての人が同じ人として普通に生活を送ることが出来るよう努めます。
理事長挨拶

西岡病院は、1922年に「西岡醫院」として那珂川河畔の当地に開設され、100年以上、地域に根付いた医療施設として、多くの方々の健康をサポートして参りました。 「温かな思いやりの中で、患者様を回復へと導く」。それが当院のモットーです。 患者様自らの回復力を引き出し、早期治癒を実現するために、スタッフ一同「身体のケア」と共に「こころのケア」を重視した、細やかな医療を実践しています。一人一人との出会いと地域社会と調和を大切に、皆様からの信頼に応えられるよう、安心安全の医療の提供に努めて参ります。
病院概要

- 病院名称
- 医療法人社団 照和会 西岡病院
- 所在地
- 〒811-1346 福岡県福岡市南区老司2-3-34
- 開設年
- 大正11年9月
- 理事長
- 西岡雄二
- 病床数
- 150床 ・内科:療養病床 30床 ・精神科:一般病床 60床/療養病床 60床
- 診療科目
- 精神科・心療内科・内科
- 診療時間
- 平日:9:00~12:00/13:00~17:00 土曜:9:00~12:00 休診:日祝日
病院沿革
- 大正11年9月
- 西岡醫院開設(無床)院長 西岡昇
- 昭和30年4月
- 内科病床認可(内科15床・結核15床)
- 昭和39年6月
- 精神科病床併設(85床)
- 昭和60年2月
- 医療法人社団 照和会設立(初代理事長 西岡徹二)
- 昭和61年2月
- 増床認可(内科30床・精神科120床)
- 平成3年7月
- 中尾診療所開設(内科・無床)
- 平成5年2月
- 西岡雄二 理事長就任
- 平成9年5月
- のぞみメンタルクリニック開設(精神科・無床
- 平成10年4月
- みどり訪問看護ステーション開設
- 平成12年4月
- 精神科病床区分変更(一般60床・療養60床)
- 平成12年5月
- 精神科デイケア(大規模)認可
- 平成18年4月
- 認知症グループホーム ソレイユ開設
- 平成26年8月
- 就労継続支援B型 ぽると開設
- 令和4年10月
- ハーモニー心のクリニック開設(精神科・無床)
院内写真



医師紹介
常勤医師
-
西岡 雄二(院長)
診療科:精神科
所属学会:日本精神神経学会・日本老年精神医学会 -
東中園聡(医局長)
診療科:精神科
所属学会:日本精神神経学会・日本精神分析学会 -
阿南多津
診療科:精神科
所属学会:日本精神神経学会・日本老年精神医学会 -
三好敦子
診療科:精神科
所属学会:日本精神神経学会 -
李竜樹
診療科:内科
所属学会:日本東洋学会・高齢者消化器病学会
非常勤医師
-
九州大学精神科医局より派遣
診療科:精神科
■ 診療日(金) -
富永浩平
診療科:内科
■ 診療日(月・土) -
西岡慧
診療科:精神科
所属学会:日本精神神経学会・日本老年精神医学会・九州精神神経学会
各部門紹介
看護部
薬剤課
作業療法室
デイケア
医療福祉相談室
栄養課
事務部
-
看護部


看護部の理念・基本方針
看護理念
私たちは患者様の生命の尊厳と人権を守る事を最優先に、患者様が安心して療養できる環境を整え、最善の看護を行うために看護職員の質の向上を図り、地域医療の支援に努めます。
基本方針
1.医療・福祉・看護の倫理を学び実践します。
2.接遇の能力向上に努めます。
3.インフォームドコンセントの充実を図ります。
4.患者様のニーズを知り、快適な療養環境を提供いたします。
5.知識と技術を身につけ、質の高い看護を提供いたします。
6.継続看護の充実を図り、社会復帰支援に努めます。教育体制
教育理念
当院の看護職員は、患者様との温かなコミュニケーションを築いた上での看護を重視しており、日々、看護観察眼とコミュニケーション技術の向上に取り組んでいます。看護師たちが自身の看護に対する自信を持てるよう、院内・院外の研修やeラーニング、看護研究などで各々の看護技術や内面的な成長を図り、自立した看護師を育てることを目指しています。
教育制度について
1.プリセプター制度 先輩看護師(プリセプター)が一定期間、新人看護師(プリセプティ)に対して、マンツーマンで臨床実践を指導する方法のことです。新採用者、異動者にこの制度を導入しています。これにより、プリセプターのキャリアアップとプリセプテイの着実な成長を支援しています。
2.クリニカルラダー制度 看護部の教育理念に基づき、一段一段キャリアを向上させていく仕組みです。看護職員の能力を評価することにより、目標が明確になり、意欲の向上を目指しています。
3.院内・院外研修制度 看護部研修会(月1回)、院外研修会、学会参加、eラーニング導入など、様々な方法で看護師の技術向上や成長の機会を設けています。
入職をお考えの方へ
それぞれのキャリアを活かしてアットホームな職場で働きませんか?
初めて精神科で働くあなたもしっかりとサポートしていきます。精神科看護師の仕事内容
・患者様と信頼関係を築き、コミュケーションを取り心のケアを行うこと
・患者様の状態の評価や判断
・セルフケアの援助
・与薬精神科看護のやりがい
・精神面での疾患を抱える患者様とって看護師の存在は大きく、患者様の回復と笑顔に直接携わることができます。
・患者様の退院後も見据えた看護ができます。
・患者様と信頼関係を築きながら退院支援を直接進めることができます。
・幅広い領域の看護スキルが活かせます。
・精神科特有の病気だけでなく、身体疾患の知識も重宝される現場であるため、思わぬところで自分の経験を活かすことができます。当院の看護部の魅力
・教育環境の充実
・風通しの良い職場環境
・職員のウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)を大切にしているところ -
薬剤課

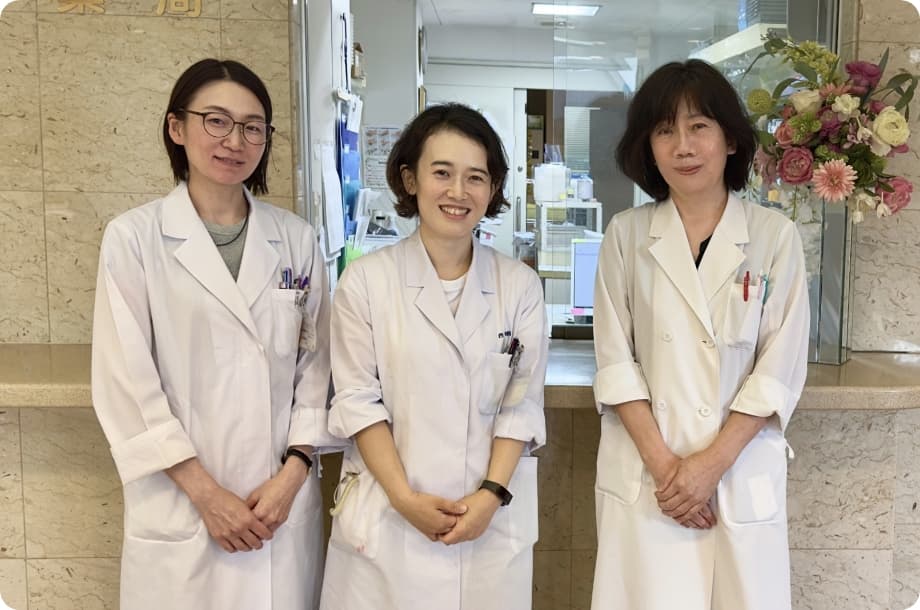
薬剤課では患者様が安心して薬物療法を受けることができるよう、薬剤師が薬のスペシャリストとして様々な活動を行っています。
業務内容
1.医薬品の適正使用・情報管理 医薬品が適正に使用されるように、医薬品の情報(安全性情報・副作用・添付文書の改訂等)を収集し、医療スタッフに提供しています。また、薬事委員会を通じて、採用医薬品の評価や医薬品の適正使用を推進しています。
2.医薬品の適正管理 院内で使用する医薬品の計画的な購入と供給、適正管理(使用量・使用期限・保管管理など)を行っています。
3.患者様へのお薬の提供 処方箋の処方鑑査及び医師への疑義照会を的確に行うことで、医薬品の安全で適正な使用に努めています。そのうえで、正確な調剤を行い、お薬を提供しています。
4.薬剤管理指導業務 入院時に持参薬や薬剤アレルギーを確認し、薬の説明や副作用モニタリングを行うことで安全で適正な薬物療法に寄与しています。患者様がお薬を理解し、安心して積極的に治療を継続していただけるように努めています。
5.チーム医療の推進 薬剤管理指導業務のほか、感染委員会や褥瘡委員会、NSTなどに参画しています。薬剤師の専門性を活かし、他の医療スタッフと協力・連携しながら患者様に薬物療法が安全・効果的に行われるように努めています。
-
作業療法室


精神科作業療法とは?
精神疾患により生活に支障をもった方々に対し、作業活動(創作的なものから日常生活に関連するものまで)を個別あるいは集団の中で利用することで、精神機能・対人関係能力・作業能力などの改善・向上をはかり、その人にとっての「より良い生活」がおくれるように援助するものです。 療養生活で心と体をゆっくり休ませたら、作業療法に参加しましょう。
作業内容
まず、レクリエーションから開始します。レクリエーションは作業療法のベースとなる大切な活動で、療養仲間と交流する良い機会にもなります。参加していくことで、ご自身のペースを取り戻していくことができます。
小グループ活動の中から必要なものを選んでレクリエーションと組み合わせ、あなた独自の作業療法スケジュールを作っていきます。 療養生活で心と体をゆっくり休ませたら、作業療法に参加しましょう。小グループ活動内容:
手工芸・スポーツ・農作業など対象
精神疾患により当院に入院されている方で、以下のようなお悩みをお持ちの方
・やる気が起こらない
・日中何をしたらよいかわからない
・他者とうまくコミュニケーションが取れない
・仕事に行けない、長続きしない など作業療法で目指すこと
・心身の活動を楽しむこと
・人と一緒に過ごせること
・生活のリズムを作ること
・良い状態の自分を発見すること など作業療法の効果
作業療法の中で作業に集中したり、他者と交わることにより、薬だけでは解決できない自分の生活を「より良くする方法」を身につけることができます。
・できたことを実感できたり評価されたりすることで、自信につながった
・人の話をきちんと聞く、自分の思いをうまく相手に伝える方法を身につけられた
・生活のリズムを整えられた
・作業に集中することで、ストレスとなることから気がまぎれた など -
デイケア
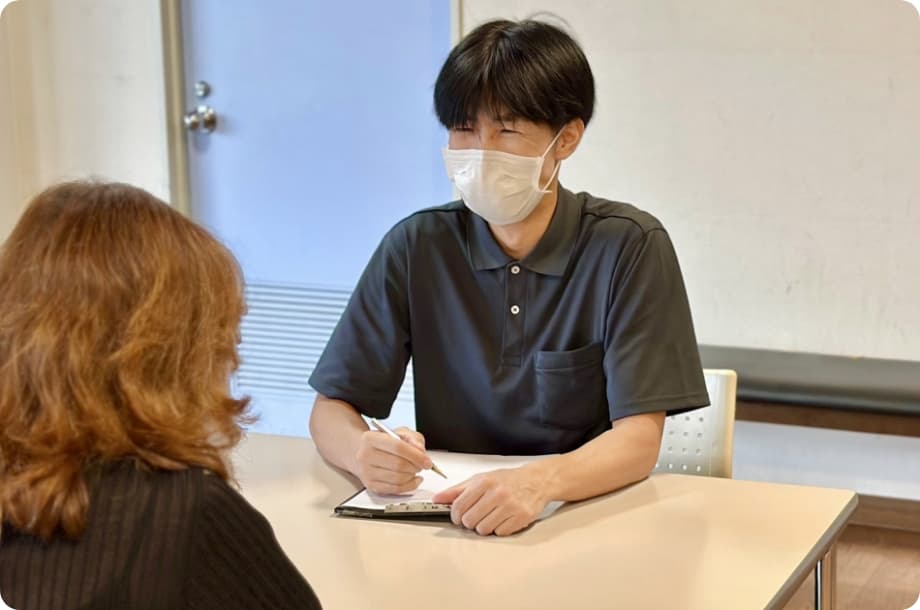

デイケアとは?
デイケア(昼間通所治療訓練)とは、地域で生活している心の病を負った方々が、治療の一環として、日中に集い、様々な活動を行いながら疾患の治療をしていく場です。
西岡病院のデイケアでは友達を作ったり、生活のリズムを身に付けたり、様々な社会経験をしたりと、より充実した社会生活が送れるようになることを目標にしています。
デイケアの活動時間 ••• 9:30〜15:30こんなお悩みありませんか?
・退院したけど、何もすることがない。
・社会復帰したい。
・人とお話したいなぁ。友達作りたいなぁ。
・毎日家にいることばかり。どこかに出かけたいけど・・・。
・朝は遅くまで寝ているし、起きていてもテレビの前でゴロゴロ。
こんなんじゃだめかな・・・。
・働きたいけど、自信がない。
・退院したのはいいけれど、また悪くなるんじゃないかと不安になる。デイケアの内容と効果
1.社会に出る前の練習 デイケアは小さな社会です。人とのコミュニケーションの取り方や病気との付き合い方などを学習することができます。また、デイケアに参加することで生活リズムを作り、睡眠の改善にも繋がります。
2.集団プログラムでの治療の場 人はホッとできる、安心して過ごすことのできる「何か」に属すことで得られる安心感を得ることで生きていくための基盤を作ります。デイケアでの「つながり」が所属感や安心感となり、心の寄りどころとなります。
3.相談ができる場 当院のデイケアは、病気や服薬、生活等、気軽に相談できる場所です。
作業療法士や看護師、医師、精神保健福祉士など、専門的な知識が豊富な担当スタッフがサポート致します。4.ピアグループ デイケアは、当事者同士でないと分からない事を共有できる場でもあります。幅広い世代のメンバーさんが来られていますので、話せる相手や同じようなお悩みを抱えた方が見つかるかもしれません。
-
医療福祉相談室


医療福祉相談室とは?
私たちは、「安心感とその人が望む暮らしのサポート」をモットーに、心の悩みや生活のしづらさを抱えるすべての方が、それぞれのペースで自分らしい暮らしを見つけていくお手伝いをしております。少しでも相談して良かったと思っていただけるよう、病院スタッフをはじめ、福祉サービスの担当者、ケアマネージャー、行政機関、地域など、相談者に関わるあらゆる人とのつながりを重視しております。当院では患者様おひとりおひとりに担当の相談員をつけさせて頂きますので、どうぞお気軽にお声掛けください。
業務内容
当院への新規受診、入院を希望される方の相談及び調整の窓口 ※詳しくは、診察の流れをご覧ください。 ※当院は予約制になります。
診察、入院をご希望の方は、相談員よりお話を伺い、医師と日程を決めさせていただきますので、必ず事前のお電話をお願いします。
092-565-5651当院外来、入院患者様の具体的な相談援助 病気の治療中には誰もが生活上、さまざまな悩みや困りごとが生じます。
以下のようなご相談をよくお受けします。
・退院後の生活が心配なので相談したい。
・医療費の支払いについて不安があり、相談したい。
・障害年金や介護保険などの制度やサービスについて相談したい。
・一人暮らしが心配なので、入所できる施設のことで相談したい。
・仕事に就きたいが、自信がないので支援をしてくれる制度について知りたい。
・相談・介護支援専門員の方からのご相談など -
栄養課


美味しい治療食の提供
患者様おひとりおひとりの身体的、内科的状況をもとに栄養管理計画を立て、食事摂取基準を作成し、それぞれにあった治療食を提供しています。
また、暦に合わせ、月1~2回の行事食を行っており、お盆やお正月のメニューだけでなく春、秋のお彼岸にはおはぎを手作りしています。家庭でのお食事を感じられるようなメニューをお出しできるよう心がけることで、入院やデイケアの患者様に喜んでいただいています。栄養指導
入院中だけでなく外来でも患者様個々に合わせた栄養指導・栄養相談を行っています。
食事内容、栄養状態に関して気になる方は、お気軽に主治医にお声かけ下さい。
健康診断後の特定保健指導も行っております。管理栄養士としてのやりがい
感染対策委員会、褥瘡対策委員会、ケースカンファレンスなどで必要な患者様のサポート、計画を実施しています。特に管理栄養士主催のNST(栄養サポートチーム)では毎月1回の会議で
全入院患者様の栄養状態の評価と検討をし、栄養管理しています。 -
事務部


業務内容
事務部は、医療事務業務の他に、経営企画・総務・人事・システム管理・施設管理など多種多様な業務を行っており、病院運営には欠かせない役割を担っています。
また、チーム医療を実践する一員として、医師・看護師・その他専門職と連携・協力を行いながら、地域に求められる病院づくりに貢献できるよう、「事務総合職」として、一人ひとりが自分で考え行動するよう努めています。当院事務部の魅力
・「いつもありがとう」「わかりやすかった」などのお礼の言葉を頂けたときにやりがいを感じる。
・部署内、他部署との連携・協力体制がある。
・診療報酬の基本から学べる。
・時間外業務が少なく、自分時間を有効に使える。など

